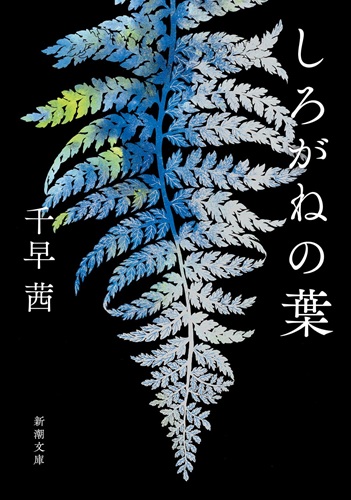
豊臣から徳川へ移行する時代を背景に、現在の島根県にあった石見銀山を舞台にした物語です。
貧しさから逃れるため、家族で村を抜ける途中親からはぐれた主人公の少女が、希代の山師に拾われ銀山で育てられながら、女へ、妻へ、母親へと成長していく物語です。
30歳になると長寿のお祝いをしたと言われるほど短命だった”銀堀(銀の採掘に従事した労働者)”自体がその時代の異端者として描かれていますが、夜目が効き闇を好み、心の内に獣を宿す少女は、その中でも際立つ異端者です。
銀堀も少女も情念のままに命を燃やして生きていますが、メラメラと燃え上がる炎ではなく、暗闇の中、妖しくしろがねに輝くシダの葉が少女の情念を象徴しています。
ドラマティックな展開があるわけではなく、時代の移ろい、少女から女への成長、女であるが故の挫折感、愛する男への愛おしさなどが淡々と描かれます。
命を削って銀を掘り続ける男たち、男たちに頼らなければ生きられない女たち。
銀の毒で短命な男たちは、自分たちの死後も女たちが生きていけるよう、新しい男に自分の妻を引き継ぎます。
異常とも言える方法で、家族を慈しみ、命を継承し死んでいく男たちには、身勝手さと哀れさが同居しています。
生きる意味を問うと言うよりは、生き続けること自体の苛烈さや尊さを訴えているような物語です。
特殊な環境で生き、歪な愛や性に激しく身を焼きつくすことでしか生きられなかった女たちと男たちの姿が、心を揺さぶる傑作です。
